 |
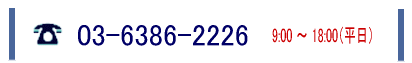 |
|
遺贈とは、遺言により財産の全部または一部を贈与することです。贈与する相手は、相続人でも相続人以外でもかまわず、また、法人や団体等でも可能です(贈与される人や団体等を受遺者と言います)。ただし、「遺留分」と言って、配偶者、第一順位、第二順位の相続人には最低限保証された相続分があるため、遺贈には注意が必要です。
また、遺言者よりも受遺者が先に亡くなった場合は、遺贈を受け取ることはできません。受遺者の相続人も遺贈を受ける権利を相続することはできません。 ■ 遺贈の主なもの
「遺贈」は、被相続人より受遺者が先に亡くなれば効力を失います。したがって、代襲相続(直系卑属が代わりに相続人になる)がおこりません。また、所有権を移転する登記手続のときには、受遺者と相続人(遺言執行者がいれば遺言執行者)が共同して申請することになります。 それに対し、「相続」の場合は、相続人が被相続人より先に亡くなっていても代襲相続となり、直系卑属が相続します。登記手続においても、相続人の単独申請となります。また、相続の対象となる土地が農地だったら、農地の移転に際して必要とされる農地法3条による農業委員会または知事の許可も不要となります。 このように、「遺贈」と「相続」では次のような違いがあります。
死因贈与契約とは、生前、特定の人と「自分が死んだら○○をあげる」という契約をすることです。贈与契約については、口約束の場合なら取り消すことができますが(民550)、書面で契約を交わすと簡単には取り消すことができません。 死因贈与契約は、自分が亡くなったら財産を与えるという内容であるため、遺言に良く似ています。そのため、死因贈与契約には、遺贈の規定が準用されます。遺言は単独行為(相手の意思に関係なく行われる行為)であるため、遺言者はいつでも遺贈を取り消すことができます。したがって、書面でされた死因贈与契約も遺贈と同様に、贈与者の意思を尊重して、撤回を認めています。ただし、負担付死因贈与で負担の履行期が贈与者の生前と定められたもので、受贈者が負担を履行している場合は、自由に撤回することは許されないとした判例があります(最判昭57.4.30)。 被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物に相続開始後も無償で居住し続けられる権利として、配偶者居住権が創設されました。この権利は遺贈の対象となります。
被相続人が所有する建物を配偶者に相続させれば、配偶者はその建物に居住できますが、たとえば、子に相続させた場合、残された配偶者が住み慣れた家に居住し続けたい気持ちがあっても、子が建物を売却したいと強く希望すれば、住み続けられなくなくなってしまう可能性があります。 そこで、平成30年の民法改正により、配偶者居住権(2020年4月1日施行)が創設され、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者が遺贈または遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、 終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになりました。 詳しくは、配偶者居住権を参照して下さい。 |
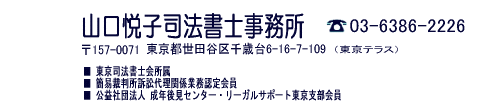 |
||